芥川賞と直木賞の受賞作家一覧です。
1935年から現在までのすべての作家の名前の読み、生年、受賞回、受賞年、受賞作をまとめています。
それぞれの賞、受賞順のまとめは以下もご覧ください。
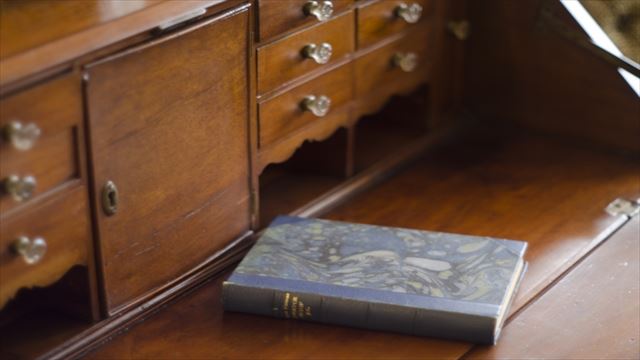
芥川賞受賞作品一覧・第1~170回のすべてまとめデータ
近年の受賞作・候補作 受賞作品すべての一覧 受賞作品該当なしの回は省略しています。 受賞回 受賞年 著者 読み 生年 受賞作 170 2023下 九段理江 くだん りえ 1990 東京都同情塔 169 2023上 市川沙央 いちかわ さおう...
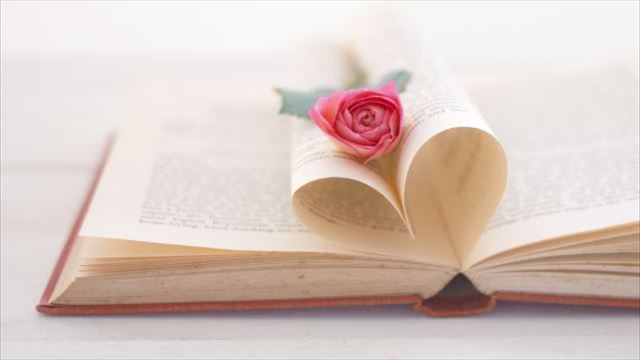
直木賞受賞作品一覧・第1~170回のすべてまとめデータ
近年の受賞作・候補作 受賞作品すべての一覧 受賞作品該当なしの回は省略しています。 受賞回 受賞年 著者 読み 生年 受賞作 170 2023下 河﨑秋子 かわさき あきこ 1979 ともぐい 〃 〃 万城目学 まきめ まなぶ 1976 八...
芥川賞・直木賞作家50音順一覧
初期状態は50音順ですべてが表示されています。
出来る事
-
表示件数の変更
-
項目ごとに昇順・降順に並び替え
-
作家名や本のタイトルで検索
※表の「賞」欄:直/直木賞、芥/芥川賞
| 著者 | 読み | 生年 | 賞 | 受賞回 | 受賞年 | 受賞作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青島幸男 | あおしま ゆきお | 1932 | 直 | 85 | 1981上 | 人間万事塞翁が丙午 |
| 青野聰 | あおの そう | 1943 | 芥 | 81 | 1979上 | 愚者の夜 |
| 青山七恵 | あおやま ななえ | 1983 | 芥 | 136 | 2006下 | ひとり日和 |
| 青山文平 | あおやま ぶんぺい | 1948 | 直 | 154 | 2015下 | つまをめとらば |
| 赤瀬川隼 | あかせがわ しゅん | 1931 | 直 | 113 | 1995上 | 白球残映 |
| 赤染晶子 | あかぞめ あきこ | 1974 | 芥 | 143 | 2010上 | 乙女の密告 |
| 朝井まかて | あさい まかて | 1959 | 直 | 150 | 2013下 | 恋歌 (れんか) |
| 朝井リョウ | あさい りょう | 1989 | 直 | 148 | 2012下 | 何者 |
| 浅田次郎 | あさだ じろう | 1951 | 直 | 117 | 1997上 | 鉄道員(ぽっぽや) |
| 朝吹真理子 | あさぶき まりこ | 1984 | 芥 | 144 | 2010下 | きことわ |
| 芦原すなお | あしはら すなお | 1949 | 直 | 105 | 1991上 | 青春デンデケデケデケ |
| 阿刀田高 | あとうだ たかし | 1935 | 直 | 81 | 1979上 | ナポレオン狂 |
| 阿部牧郎 | あべ まきお | 1933 | 直 | 98 | 1987下 | それぞれの終楽章 |
| 阿部和重 | あべ かずしげ | 1968 | 芥 | 132 | 2004下 | グランド・フィナーレ |
| 安部公房 | あべ こうぼう | 1924 | 芥 | 25 | 1951上 | 壁 |
| 安部龍太郎 | あべ りゅうたろう | 1955 | 直 | 148 | 2012下 | 等伯 |
| 新井満 | あらい まん | 1946 | 芥 | 99 | 1988上 | 尋ね人の時間 |
| 有明夏夫 | ありあけ なつお | 1936 | 直 | 80 | 1978下 | 大浪花諸人往来 |
| 有馬頼義 | ありま よりちか | 1918 | 直 | 31 | 1954上 | 終身未決囚 |
| 泡坂妻夫 | あわさか つまお | 1933 | 直 | 103 | 1990上 | 蔭桔梗 |
| 安西篤子 | あんざい あつこ | 1927 | 直 | 52 | 1964下 | 張少子(チャンシャオツ)の話 |
| 安藤鶴夫 | あんどう つるお | 1908 | 直 | 50 | 1963下 | 巷談 本牧亭 |
| 李良枝 | い やんじ | 1955 | 芥 | 100 | 1988下 | 由煕 |
| 生島治郎 | いくしま じろう | 1933 | 直 | 57 | 1967上 | 追いつめる |
| 池井戸潤 | いけいど じゅん | 1963 | 直 | 145 | 2011上 | 下町ロケット |
| 池澤夏樹 | いけざわ なつき | 1945 | 芥 | 98 | 1987下 | スティル・ライフ |
| 池田満寿夫 | いけだ ますお | 1934 | 芥 | 77 | 1977上 | エーゲ海に捧ぐ |
| 池波正太郎 | いけなみ しょうたろう | 1923 | 直 | 43 | 1960上 | 錯乱 |
| 石井遊佳 | いしい ゆうか | 1963 | 芥 | 158 | 2017下 | 百年泥 |
| 石川淳 | いしかわ じゅん | 1899 | 芥 | 4 | 1936下 | 普賢 |
| 石川達三 | いしかわ たつぞう | 1905 | 芥 | 1 | 1935上 | 蒼氓(そうぼう) |
| 石川利光 | いしかわ としみつ | 1961 | 芥 | 25 | 1951上 | 春の草 他 |
| 石沢麻依 | いしざわ まい | 1980 | 芥 | 165 | 2021上 | 貝に続く場所にて |
| 石田衣良 | いしだ いら | 1960 | 直 | 129 | 2003上 | 4TEEN |
| 石塚喜久三 | いしづか きくぞう | 1904 | 芥 | 17 | 1943上 | 纏足の頃 |
| 石原慎太郎 | いしはら しんたろう | 1932 | 芥 | 34 | 1955下 | 太陽の季節 |
| 伊集院静 | いじゅういん しずか | 1950 | 直 | 107 | 1992上 | 受け月 |
| 磯崎憲一郎 | いそざき けんいちろう | 1965 | 芥 | 141 | 2009上 | 終の住処 |
| 市川沙央 | いちかわ さおう | 1979 | 芥 | 169 | 2023上 | ハンチバック |
| 五木寛之 | いつき ひろゆき | 1932 | 直 | 56 | 1966下 | 蒼ざめた馬を見よ |
| 井出孫六 | いで まごろく | 1931 | 直 | 72 | 1974下 | アトラス伝説 |
| 伊藤たかみ | いとう たかみ | 1971 | 芥 | 135 | 2006上 | 八月の路上に捨てる |
| 伊藤桂一 | いとう けいいち | 1917 | 直 | 46 | 1961下 | 螢の河 |
| 井戸川射子 | いとがわ いこ | 1987 | 芥 | 168 | 2022下 | この世の喜びよ |
| 絲山秋子 | いとやま あきこ | 1966 | 芥 | 134 | 2005下 | 沖で待つ |
| 井上ひさし | いのうえ ひさし | 1934 | 直 | 67 | 1972上 | 手鎖心中 |
| 井上荒野 | いのうえ あれの | 1961 | 直 | 139 | 2008上 | 切羽へ |
| 井上靖 | いのうえ やすし | 1907 | 芥 | 22 | 1949下 | 闘牛 |
| 井伏鱒二 | いぶせ ますじ | 1898 | 直 | 6 | 1937下 | ジョン萬次郎漂流記・その他 |
| 今村翔吾 | いまむら しょうご | 1984 | 直 | 166 | 2021下 | 塞王の楯 |
| 今村夏子 | いまむら なつこ | 1980 | 芥 | 161 | 2019上 | むらさきのスカートの女 |
| 色川武大 | いろかわ たけひろ | 1929 | 直 | 79 | 1978上 | 離婚 |
| 宇佐見りん | うさみ りん | 1999 | 芥 | 164 | 2020下 | 推し、燃ゆ |
| 宇能鴻一郎 | うの こういちろう | 1934 | 芥 | 46 | 1961下 | 鯨神 |
| 梅崎春生 | うめざき はるお | 1915 | 直 | 32 | 1954下 | ボロ家の春秋 |
| 江國香織 | えくに かおり | 1964 | 直 | 130 | 2003下 | 号泣する準備はできていた |
| 江崎誠致 | えさき まさのり | 1922 | 直 | 37 | 1957上 | ルソンの谷間 |
| 海老沢泰久 | えびさわ やすひさ | 1950 | 直 | 111 | 1994上 | 帰郷 |
| 円城塔 | えんじょう とう | 1972 | 芥 | 146 | 2011下 | 道化師の蝶 |
| 遠藤周作 | えんどう しゅうさく | 1923 | 芥 | 33 | 1955上 | 白い人 |
| 逢坂剛 | おうさか ごう | 1943 | 直 | 96 | 1986下 | カディスの赤い星 |
| 大池唯雄 | おおいけ ただお | 1908 | 直 | 8 | 1938下 | 兜首・秋田口の兄弟 |
| 大江健三郎 | おおえ けんざぶろう | 1935 | 芥 | 39 | 1958上 | 飼育 |
| 大岡玲 | おおおか あきら | 1958 | 芥 | 102 | 1989下 | 表層生活 |
| 大沢在昌 | おおさわ ありまさ | 1956 | 直 | 110 | 1993下 | 新宿鮫 無間人形 |
| 大島真寿美 | おおしま ますみ | 1962 | 直 | 161 | 2019上 | 渦 妹背山婦女庭訓 魂結び |
| 大城立裕 | おおしろ たつひろ | 1925 | 芥 | 57 | 1967上 | カクテル・パーティー |
| 大庭みな子 | おおば みなこ | 1930 | 芥 | 59 | 1968上 | 三匹の蟹 |
| 岡田誠三 | おかだ せいぞう | 1913 | 直 | 19 | 1944上 | ニューギニヤ山岳戦 |
| 岡松和夫 | おかまつ かずお | 1931 | 芥 | 74 | 1975下 | 志賀島 |
| 小川哲 | おがわ さとし | 1986 | 直 | 168 | 2022下 | 地図と拳 |
| 小川洋子 | おがわ ようこ | 1962 | 芥 | 104 | 1990下 | 妊娠カレンダー |
| 荻野アンナ | おぎの あんな | 1956 | 芥 | 105 | 1991上 | 背負い水 |
| 荻原浩 | おぎわら ひろし | 1956 | 直 | 155 | 2016上 | 海の見える理髪店 |
| 奥泉光 | おくいずみ ひかる | 1956 | 芥 | 110 | 1993下 | 石の来歴 |
| 奥田英朗 | おくだ ひでお | 1959 | 直 | 131 | 2004上 | 空中ブランコ |
| 尾崎一雄 | おざき かずお | 1899 | 芥 | 5 | 1937上 | 暢氣眼鏡 他 |
| 長部日出雄 | おさべ ひでお | 1934 | 直 | 69 | 1973上 | 津軽世去れ節・津軽じょんから節 |
| 小田嶽夫 | おだ たけお | 1900 | 芥 | 3 | 1936上 | 城外 |
| 尾辻克彦 | おつじ かつひこ | 1937 | 芥 | 84 | 1980下 | 父が消えた |
| 乙川優三郎 | おとかわ ゆうざぶろう | 1953 | 直 | 127 | 2002上 | 生きる |
| 小野正嗣 | おの まさつぐ | 1970 | 芥 | 152 | 2014下 | 九年前の祈り |
| 小尾十三 | おび じゅうぞう | 1908 | 芥 | 19 | 1944上 | 登攀 |
| 小山田浩子 | おやまだ ひろこ | 1983 | 芥 | 150 | 2013下 | 穴 |
| 恩田陸 | おんだ りく | 1964 | 直 | 156 | 2016下 | 蜜蜂と遠雷 |
| 海音寺潮五郎 | かいおんじ ちょうごろう | 1901 | 直 | 3 | 1936上 | 天正女合戦・武道傳來記 |
| 開高健 | かいこう たけし | 1930 | 芥 | 38 | 1957下 | 裸の王様 |
| 垣根涼介 | かきね りょうすけ | 1966 | 直 | 169 | 2023上 | 極楽征夷大将軍 |
| 角田光代 | かくた みつよ | 1967 | 直 | 132 | 2004下 | 対岸の彼女 |
| 景山民夫 | かげやま たみお | 1947 | 直 | 99 | 1988上 | 遠い海から来たCOO |
| 笠原淳 | かさはらじゅん | 1935 | 芥 | 90 | 1983下 | 杢二の世界 |
| 鹿島田真希 | かしまだ まき | 1976 | 芥 | 147 | 2012上 | 冥土めぐり |
| 柏原兵三 | かしわばら ひょうぞう | 1933 | 芥 | 58 | 1967下 | 徳山道助の帰郷 |
| 門井慶喜 | かどい よしのぶ | 1971 | 直 | 158 | 2017下 | 銀河鉄道の父 |
| 加藤幸子 | かとう ゆきこ | 1936 | 芥 | 88 | 1982下 | 夢の壁 |
| 金城一紀 | かねしろ かずき | 1968 | 直 | 123 | 2000上 | GO |
| 金原ひとみ | かねはら ひとみ | 1983 | 芥 | 130 | 2003下 | 蛇にピアス |
| 唐十郎 | から じゅうろう | 1940 | 芥 | 88 | 1982下 | 佐川君からの手紙 |
| 川上弘美 | かわかみ ひろみ | 1958 | 芥 | 115 | 1996上 | 蛇を踏む |
| 川上未映子 | かわかみ みえこ | 1976 | 芥 | 138 | 2007下 | 乳と卵 |
| 川口松太郎 | かわぐち まつたろう | 1899 | 直 | 1 | 1935上 | 鶴八鶴次郎・風流深川唄 その他 |
| 川越宗一 | かわごえ そういち | 1988 | 直 | 162 | 2019下 | 熱源 |
| 河﨑秋子 | かわさき あきこ | 1979 | 直 | 170 | 2023下 | ともぐい |
| 河内仙介 | かわち せんすけ | 1898 | 直 | 11 | 1940上 | 軍事郵便 |
| 川村晃 | かわむら あきら | 1927 | 芥 | 47 | 1962上 | 美談の出発 |
| 神吉拓郎 | かんき たくろう | 1928 | 直 | 90 | 1983下 | 私生活 |
| 神崎武雄 | かんざき たけお | 1906 | 直 | 16 | 1942下 | 寛容・その他 |
| 木内昇 | きうち のぼり | 1967 | 直 | 144 | 2010下 | 漂砂のうたう |
| 木々高太郎 | きぎ たかたろう | 1897 | 直 | 4 | 1936下 | 人生の阿呆 |
| 菊村到 | きくむら いたる | 1925 | 芥 | 37 | 1957上 | 硫黄島 |
| 木崎さと子 | きざき さとこ | 1939 | 芥 | 92 | 1984下 | 青桐 |
| 北杜夫 | きた もりお | 1927 | 芥 | 43 | 1960上 | 夜と霧の隅で |
| 北原亞以子 | きたはら あいこ | 1938 | 直 | 109 | 1993上 | 恋忘れ草 |
| 北村薫 | きたむら かおる | 1949 | 直 | 141 | 2009上 | 鷺と雪 |
| 木村荘十 | きむら そうじゅう | 1897 | 直 | 13 | 1941上 | 雲南守備兵 |
| 邱永漢 | きゅう えいかん | 1924 | 直 | 34 | 1955下 | 香港 |
| 京極夏彦 | きょうごく なつひこ | 1963 | 直 | 130 | 2003下 | 後巷説百物語 |
| 清岡卓行 | きよおか たかゆき | 1922 | 芥 | 62 | 1969下 | アカシヤの大連 |
| 桐野夏生 | きりの なつお | 1951 | 直 | 121 | 1999上 | 柔らかな頬 |
| 九段理江 | くだん りえ | 1990 | 芥 | 170 | 2023下 | 東京都同情塔 |
| 窪美澄 | くぼ みすみ | 1965 | 直 | 167 | 2022上 | 夜に星を放つ |
| 熊谷達也 | くまがい たつや | 1958 | 直 | 131 | 2004上 | 邂逅の森 |
| 倉光俊夫 | くらみつ としお | 1908 | 芥 | 16 | 1942下 | 連絡員 |
| 車谷長吉 | くるまたに ちょうきつ | 1945 | 直 | 119 | 1998上 | 赤目四十八瀧心中未遂 |
| 胡桃沢耕史 | くるみざわ こうし | 1925 | 直 | 89 | 1983上 | 黒パン俘虜記 |
| 黒岩重吾 | くろいわ じゅうご | 1924 | 直 | 44 | 1960下 | 背徳のメス |
| 黒川博行 | くろかわ ひろゆき | 1949 | 直 | 151 | 2014上 | 破門 |
| 黒田夏子 | くろだ なつこ | 1937 | 芥 | 148 | 2012下 | abさんご |
| 玄月 | げんげつ | 1965 | 芥 | 122 | 1999下 | 蔭の棲みか |
| 源氏鶏太 | げんじ けいた | 1912 | 直 | 25 | 1951上 | 英語屋さん・その他 |
| 玄侑宗久 | げんゆう そうきゅう | 1956 | 芥 | 125 | 2001上 | 中陰の花 |
| 小池真理子 | こいけ まりこ | 1952 | 直 | 114 | 1995下 | 恋 |
| 郷静子 | ごう しずこ | 1929 | 芥 | 68 | 1972下 | れくいえむ |
| 河野多惠子 | こうの たえこ | 1926 | 芥 | 49 | 1963上 | 蟹 |
| 小島信夫 | こじま のぶお | 1915 | 芥 | 32 | 1954下 | アメリカン・スクール |
| 小谷剛 | こたに つよし | 1924 | 芥 | 21 | 1949上 | 確証 |
| 後藤紀一 | ごとう きいち | 1915 | 芥 | 49 | 1963上 | 少年の橋 |
| 五味康祐 | ごみ やすすけ | 1921 | 芥 | 28 | 1952下 | 喪神 |
| 米谷ふみ子 | こめたに ふみこ | 1930 | 芥 | 94 | 1985下 | 過越しの祭 |
| 小山いと子 | こやま いとこ | 1901 | 直 | 23 | 1950上 | 執行猶予 |
| 今官一 | こん かんいち | 1909 | 直 | 35 | 1956上 | 壁の花 |
| 今東光 | こん とうこう | 1898 | 直 | 36 | 1956下 | お吟さま |
| 今日出海 | こん ひでみ | 1903 | 直 | 23 | 1950上 | 天皇の帽子 |
| 西條奈加 | さいじょう なか | 1984 | 直 | 164 | 2020下 | 心淋し川 |
| 早乙女貢 | さおとめ みつぐ | 1926 | 直 | 60 | 1968下 | 僑人の檻 |
| 阪田寛夫 | さかた ひろお | 1925 | 芥 | 72 | 1974下 | 土の器 |
| 佐木隆三 | さき りゅうぞう | 1937 | 直 | 74 | 1975下 | 復讐するは我にあり |
| 桜木紫乃 | さくらぎ しの | 1965 | 直 | 149 | 2013上 | ホテルローヤル |
| 櫻田常久 | さくらだ つねひさ | 1897 | 芥 | 12 | 1940下 | 平賀源内 |
| 桜庭一樹 | さくらば かずき | 1971 | 直 | 138 | 2007下 | 私の男 |
| 佐々木譲 | ささき じょう | 1950 | 直 | 142 | 2009下 | 廃墟に乞う |
| 笹倉明 | ささくら あきら | 1948 | 直 | 101 | 1989上 | 遠い国からの殺人者 |
| 佐藤愛子 | さとう あいこ | 1923 | 直 | 61 | 1969上 | 戦いすんで日が暮れて |
| 佐藤厚志 | さとう あつし | 1982 | 芥 | 168 | 2022下 | 荒地の家族 |
| 佐藤究 | さとう きわむ | 1977 | 直 | 165 | 2021上 | テスカトリポカ |
| 佐藤雅美 | さとう まさよし | 1941 | 直 | 110 | 1993下 | 恵比寿屋喜兵衛手控え |
| 佐藤賢一 | さとう けんいち | 1968 | 直 | 121 | 1999上 | 王妃の離婚 |
| 佐藤正午 | さとう しょうご | 1955 | 直 | 157 | 2017上 | 月の満ち欠け |
| 佐藤得二 | さとう とくじ | 1899 | 直 | 49 | 1963上 | 女のいくさ |
| 寒川光太郎 | さむかわ こうたろう | 1908 | 芥 | 10 | 1939下 | 密獵者 |
| 澤田瞳子 | さわだ とうこ | 1977 | 直 | 165 | 2021上 | 星落ちて、なお |
| 重兼芳子 | しげかね よしこ | 1927 | 芥 | 81 | 1979上 | やまあいの煙 |
| 重松清 | しげまつ きよし | 1963 | 直 | 124 | 2000下 | ビタミンF |
| 篠田節子 | しのだ せつこ | 1955 | 直 | 117 | 1997上 | 女たちのジハード |
| 司馬遼太郎 | しば りょうたろう | 1923 | 直 | 42 | 1959下 | 梟の城 |
| 斯波四郎 | しば しろう | 1910 | 芥 | 41 | 1959上 | 山塔 |
| 芝木好子 | しばき よしこ | 1914 | 芥 | 14 | 1941下 | 青果の市 |
| 柴崎友香 | しばさき ともか | 1973 | 芥 | 151 | 2014上 | 春の庭 |
| 柴田錬三郎 | しばた れんざぶろう | 1917 | 直 | 26 | 1951下 | イエスの裔 |
| 柴田翔 | しばた しょう | 1935 | 芥 | 51 | 1964上 | されどわれらが日々 |
| 島本理生 | しまもと りお | 1983 | 直 | 159 | 2018上 | ファーストラヴ |
| 清水基吉 | しみず もとよし | 1918 | 芥 | 20 | 1944下 | 雁立 |
| 志茂田景樹 | しもだ かげき | 1940 | 直 | 83 | 1980上 | 黄色い牙 |
| 朱川湊人 | しゅかわ みなと | 1963 | 直 | 133 | 2005上 | 花まんま |
| 庄司薫 | しょうじ かおる | 1937 | 芥 | 61 | 1969上 | 赤頭巾ちゃん気をつけて |
| 庄野潤三 | しょうの じゅんぞう | 1921 | 芥 | 32 | 1954下 | プールサイド小景 |
| 笙野頼子 | しょうの よりこ | 1956 | 芥 | 111 | 1994上 | タイムスリップ・コンビナート |
| 白石一文 | しらいし かずふみ | 1958 | 直 | 142 | 2009下 | ほかならぬ人へ |
| 白石一郎 | しらいし いちろう | 1931 | 直 | 97 | 1987上 | 海王伝 |
| 城山三郎 | しろやま さぶろう | 1927 | 直 | 40 | 1958下 | 総会屋錦城 |
| 真藤順丈 | しんどう じゅんじょう | 1977 | 直 | 160 | 2018下 | 宝島 |
| 榛葉英治 | しんば えいじ | 1912 | 直 | 39 | 1958上 | 赤い雪 |
| 新橋遊吉 | しんばし ゆうきち | 1933 | 直 | 54 | 1965下 | 八百長 |
| 杉本苑子 | すぎもと そのこ | 1925 | 直 | 48 | 1962下 | 孤愁の岸 |
| 杉本章子 | すぎもと あきこ | 1953 | 直 | 100 | 1988下 | 東京新大橋雨中図 |
| 杉森久英 | すぎもり ひさひで | 1912 | 直 | 47 | 1962上 | 天才と狂人の間 |
| 砂川文次 | すなかわ ぶんじ | 1990 | 芥 | 166 | 2021下 | ブラックボックス |
| 諏訪哲史 | すわ てつし | 1969 | 芥 | 137 | 2007上 | アサッテの人 |
| 青来有一 | せいらい ゆういち | 1958 | 芥 | 124 | 2000下 | 聖水 |
| 大道珠貴 | だいどう たまき | 1966 | 芥 | 128 | 2002下 | しょっぱいドライブ |
| 田岡典夫 | たおか のりお | 1908 | 直 | 16 | 1942下 | 強情いちご・その他 |
| 高井有一 | たかい ゆういち | 1932 | 芥 | 54 | 1965下 | 北の河 |
| 高樹のぶ子 | たかぎ のぶこ | 1946 | 芥 | 90 | 1983下 | 光抱く友よ |
| 高城修三 | たかぎ しゅうぞう | 1947 | 芥 | 78 | 1977下 | 榧の木祭り |
| 高瀬隼子 | たかせ じゅんこ | 1988 | 芥 | 167 | 2022上 | おいしいごはんが食べられますように |
| 高橋義夫 | たかはし よしお | 1945 | 直 | 106 | 1991下 | 狼奉行 |
| 高橋弘希 | たかはし ひろき | 1979 | 芥 | 159 | 2018上 | 送り火 |
| 高橋克彦 | たかはし かつひこ | 1947 | 直 | 106 | 1991下 | 緋(あか)い記憶 |
| 高橋三千綱 | たかはし みちつな | 1948 | 芥 | 79 | 1978上 | 九月の空 |
| 高橋治 | たかはし おさむ | 1929 | 直 | 90 | 1983下 | 秘伝 |
| 高橋揆一郎 | たかはし きいちろう | 1928 | 芥 | 79 | 1978上 | 伸予 |
| 高村薫 | たかむら かおる | 1953 | 直 | 109 | 1993上 | マークスの山 |
| 高山羽根子 | たかやま はねこ | 1975 | 芥 | 163 | 2020上 | 首里の馬 |
| 多岐川恭 | たきがわ きょう | 1994 | 直 | 40 | 1958下 | 落ちる |
| 滝口悠生 | たきぐち ゆうしょう | 1982 | 芥 | 154 | 2015下 | 死んでいない者 |
| 瀧澤美恵子 | たきざわ みえこ | 1939 | 芥 | 102 | 1989下 | ネコババのいる町で |
| 田久保英夫 | たくぼ ひでお | 1928 | 芥 | 61 | 1969上 | 深い河 |
| 多田裕計 | ただ ゆうけい | 1912 | 芥 | 13 | 1941上 | 長江デルタ |
| 橘外男 | たちばな そとお | 1894 | 直 | 7 | 1938上 | ナリン殿下への回想 |
| 立原正秋 | たちはら まさあき | 1926 | 直 | 55 | 1966上 | 白い罌粟 |
| 立野信之 | たての のぶゆき | 1903 | 直 | 28 | 1952下 | 叛乱 |
| 田中小実昌 | たなか こみまさ | 1925 | 直 | 81 | 1979上 | 浪曲師朝日丸の話・ミミのこと |
| 田中慎弥 | たなか しんや | 1972 | 芥 | 146 | 2011下 | 共喰い |
| 田辺聖子 | たなべ せいこ | 1928 | 芥 | 50 | 1963下 | 感傷旅行 センチメンタル・ジャーニィ |
| 多和田葉子 | たわだ ようこ | 1960 | 芥 | 108 | 1992下 | 犬婿入り |
| 檀一雄 | だん かずお | 1912 | 直 | 24 | 1950下 | 真説石川五右衛門・長恨歌 |
| 千葉治平 | ちば じへい | 1921 | 直 | 54 | 1965下 | 虜愁記 |
| 千早茜 | ちはや あかね | 1979 | 直 | 168 | 2022下 | しろがねの葉 |
| 陳舜臣 | ちん しゅんしん | 1924 | 直 | 60 | 1968下 | 青玉獅子香炉 |
| つかこうへい | つか こうへい | 1948 | 直 | 86 | 1981下 | 蒲田行進曲 |
| 辻仁成 | つじ ひとなり | 1959 | 芥 | 116 | 1996下 | 海峡の光 |
| 辻亮一 | つじ りょういち | 1914 | 芥 | 23 | 1950上 | 異邦人 |
| 辻原登 | つじはら のぼる | 1945 | 芥 | 103 | 1990上 | 村の名前 |
| 辻村深月 | つじむら みづき | 1980 | 直 | 147 | 2012上 | 鍵のない夢を見る |
| 堤千代 | つつみ ちよ | 1955 | 直 | 11 | 1940上 | 小指・その他 |
| 綱淵謙錠 | つなぶち けんじょう | 1924 | 直 | 67 | 1972上 | 斬―ざん |
| 津村記久子 | つむら きくこ | 1978 | 芥 | 140 | 2008下 | ポトスライムの舟 |
| 津村節子 | つむら せつこ | 1928 | 芥 | 53 | 1965上 | 玩具 |
| 津本陽 | つもと よう | 1929 | 直 | 79 | 1978上 | 深重の海 |
| 鶴田知也 | つるた ともや | 1902 | 芥 | 3 | 1936上 | コシャマイン記 |
| 出久根達郎 | でくね たつろう | 1944 | 直 | 108 | 1992下 | 佃島ふたり書房 |
| 寺内大吉 | てらうち だいきち | 1921 | 直 | 44 | 1960下 | はぐれ念仏 |
| 天童荒太 | てんどう あらた | 1960 | 直 | 140 | 2008下 | 悼む人 |
| 藤堂志津子 | とうどう しづこ | 1949 | 直 | 100 | 1988下 | 熟れてゆく夏 |
| 東野邊薫 | とうのべ かおる | 1902 | 芥 | 18 | 1943下 | 和紙 |
| 遠野遥 | とおの はるか | 1991 | 芥 | 163 | 2020上 | 破局 |
| 戸川幸夫 | とがわ ゆきお | 1912 | 直 | 32 | 1954下 | 高安犬物語 |
| 常盤新平 | ときわ しんぺい | 1931 | 直 | 96 | 1986下 | 遠いアメリカ |
| 戸板康二 | とさか やすじ | 1915 | 直 | 42 | 1959下 | 團十郎切腹事件 |
| 冨澤有爲男 | とみざわ ういお | 1902 | 芥 | 4 | 1936下 | 地中海 |
| 富田常雄 | とみた つねお | 1904 | 直 | 21 | 1949上 | 面・刺青 |
| 豊田穣 | とよだ じょう | 1920 | 直 | 64 | 1970下 | 長良川 |
| 永井紗耶子 | ながい さやこ | 1977 | 直 | 169 | 2023上 | 木挽町のあだ討ち |
| 永井路子 | ながい みちこ | 1925 | 直 | 52 | 1964下 | 炎環 |
| 中上健次 | なかがみ けんじ | 1946 | 芥 | 74 | 1975下 | 岬 |
| 中里恒子 | なかざと つねこ | 1909 | 芥 | 8 | 1938下 | 乗合馬車 他 |
| 中島京子 | なかじま きょうこ | 1964 | 直 | 143 | 2010上 | 小さいおうち |
| 長嶋有 | ながしま ゆう | 1972 | 芥 | 126 | 2001下 | 猛スピードで母は |
| なかにし礼 | なかにし れい | 1938 | 直 | 122 | 1999下 | 長崎ぶらぶら節 |
| 中村彰彦 | なかむら あきひこ | 1949 | 直 | 111 | 1994上 | 二つの山河 |
| 中村正軌 | なかむら まさのり | 1928 | 直 | 84 | 1980下 | 元首の謀叛 |
| 中村文則 | なかむら ふみのり | 1977 | 芥 | 133 | 2005上 | 土の中の子供 |
| 中山義秀 | なかやま ぎしゅう | 1900 | 芥 | 7 | 1938上 | 厚物咲 |
| 南木佳士 | なぎ けいし | 1951 | 芥 | 100 | 1988下 | ダイヤモンドダスト |
| 南條範夫 | なんじょう のりお | 1908 | 直 | 35 | 1956上 | 燈台鬼 |
| 難波利三 | なんば としぞう | 1936 | 直 | 91 | 1984上 | てんのじ村 |
| 西加奈子 | にし かなこ | 1977 | 直 | 152 | 2014下 | サラバ ! |
| 西木正明 | にしき まさあき | 1940 | 直 | 99 | 1988上 | 凍(しば)れる瞳 |
| 西村賢太 | にしむら けんた | 1967 | 芥 | 144 | 2010下 | 苦役列車 |
| 新田次郎 | にった じろう | 1912 | 直 | 34 | 1955下 | 強力伝 |
| 沼田真佑 | ぬまた しんすけ | 1978 | 芥 | 157 | 2017上 | 影裏 |
| ねじめ正一 | ねじめ しょういち | 1948 | 直 | 101 | 1989上 | 高円寺純情商店街 |
| 野坂昭如 | のさか あきゆき | 1930 | 直 | 58 | 1967下 | アメリカひじき・火垂るの墓 |
| 乃南アサ | のなみ あさ | 1960 | 直 | 115 | 1996上 | 凍える牙 |
| 野呂邦暢 | のろ くにのぶ | 1937 | 芥 | 70 | 1973下 | 草のつるぎ |
| 馳星周 | はせ せいしゅう | 1965 | 直 | 163 | 2020 | 少年と犬 |
| 長谷健 | はせ けん | 1904 | 芥 | 9 | 1939上 | あさくさの子供 |
| 羽田圭介 | はだ けいすけ | 1985 | 芥 | 153 | 2015上 | スクラップ・アンド・ビルド |
| 畑山博 | はたやま ひろし | 1935 | 芥 | 67 | 1972上 | いつか汽笛を鳴らして |
| 花村萬月 | はなむら まんげつ | 1955 | 芥 | 119 | 1998上 | ゲルマニウムの夜 |
| 葉室麟 | はむろ りん | 1951 | 直 | 146 | 2011下 | 蜩ノ記 (ひぐらしのき) |
| 林京子 | はやし きょうこ | 1930 | 芥 | 73 | 1975上 | 祭りの場 |
| 林真理子 | はやし まりこ | 1954 | 直 | 94 | 1985下 | 最終便に間に合えば |
| 原尞 | はら りょう | 1946 | 直 | 102 | 1989下 | 私が殺した少女 |
| 半田義之 | はんだ よしゆき | 1911 | 芥 | 9 | 1939上 | 鶏騒動 |
| 坂東眞砂子 | ばんどう まさこ | 1958 | 直 | 116 | 1996下 | 山妣 |
| 半村良 | はんむら りょう | 1933 | 直 | 72 | 1974下 | 雨やどり |
| 東峰夫 | ひがし みねお | 1938 | 芥 | 66 | 1971下 | オキナワの少年 |
| 東野圭吾 | ひがしの けいご | 1958 | 直 | 134 | 2005下 | 容疑者Xの献身 |
| 東山彰良 | ひがしやま あきら | 1968 | 直 | 153 | 2015上 | 流 |
| 久生十蘭 | ひさお じゅうらん | 1902 | 直 | 26 | 1951下 | 鈴木主水 |
| 火野葦平 | ひの あしへい | 1907 | 芥 | 6 | 1937下 | 糞尿譚 |
| 日野啓三 | ひの けいぞう | 1929 | 芥 | 72 | 1974下 | あの夕陽 |
| 姫野カオルコ | ひめの かおるこ | 1958 | 直 | 150 | 2013下 | 昭和の犬 |
| 平岩弓枝 | ひらいわ ゆみえ | 1932 | 直 | 41 | 1959上 | 鏨師 |
| 平野啓一郎 | ひらの けいいちろう | 1975 | 芥 | 120 | 1998下 | 日蝕 |
| 深田祐介 | ふかだ ゆうすけ | 1931 | 直 | 87 | 1982上 | 炎熱商人 |
| 藤井重夫 | ふじい しげお | 1916 | 直 | 53 | 1965上 | 虹 |
| 藤沢周 | ふじさわ しゅう | 1959 | 芥 | 119 | 1998上 | ブエノスアイレス午前零時 |
| 藤沢周平 | ふじさわ しゅうへい | 1927 | 直 | 69 | 1973上 | 暗殺の年輪 |
| 藤田宜永 | ふじた よしなが | 1950 | 直 | 125 | 2001上 | 愛の領分 |
| 藤野可織 | ふじの かおり | 1980 | 芥 | 149 | 2013上 | 爪と目 |
| 藤野千夜 | ふじの ちや | 1962 | 芥 | 122 | 1999下 | 夏の約束 |
| 藤本義一 | ふじもと ぎいち | 1933 | 直 | 71 | 1974上 | 鬼の詩 |
| 藤原伊織 | ふじわら いおり | 1948 | 直 | 114 | 1995下 | テロリストのパラソル |
| 藤原審爾 | ふじわら しんじ | 1921 | 直 | 27 | 1952上 | 罪な女・その他 |
| 藤原智美 | ふじわら ともみ | 1955 | 芥 | 107 | 1992上 | 運転士 |
| 船戸与一 | ふなど よいち | 1944 | 直 | 123 | 2000上 | 虹の谷の五月 |
| 古井由吉 | ふるい よしきち | 1937 | 芥 | 64 | 1970下 | 杳子 |
| 古川薫 | ふるかわ かおる | 1925 | 直 | 104 | 1990下 | 漂泊者のアリア |
| 古川真人 | ふるかわ まこと | 1988 | 芥 | 162 | 2019下 | 背高泡立草 |
| 古山高麗雄 | ふるやま こまお | 1920 | 芥 | 63 | 1970上 | プレオー8の夜明け |
| 辺見庸 | へんみ よう | 1944 | 芥 | 105 | 1991上 | 自動起床装置 |
| 保坂和志 | ほさか かずし | 1956 | 芥 | 113 | 1995上 | この人の閾 |
| 星川清司 | ほしかわ せいじ | 1921 | 直 | 102 | 1989下 | 小伝抄 |
| 堀田善衛 | ほった よしえ | 1918 | 芥 | 26 | 1951下 | 広場の孤独・漢奸その他 |
| 穂積驚 | ほづみ みはる | 1912 | 直 | 36 | 1956下 | 勝烏 |
| 堀江敏幸 | ほりえ としゆき | 1964 | 芥 | 124 | 2000下 | 熊の敷石 |
| 万城目学 | まきめ まなぶ | 1976 | 直 | 170 | 2023下 | 八月の御所グラウンド |
| 又吉栄喜 | またよし えいき | 1947 | 芥 | 114 | 1995下 | 豚の報い |
| 又吉直樹 | またよし なおき | 1980 | 芥 | 153 | 2015上 | 火花 |
| 町田康 | まちだ こう | 1962 | 芥 | 123 | 2000上 | きれぎれ |
| 町屋良平 | まちや りょうへい | 1983 | 芥 | 160 | 2018下 | 1R1分34秒 |
| 松井今朝子 | まつい けさこ | 1953 | 直 | 137 | 2007上 | 吉原手引草 |
| 松浦寿輝 | まつうら ひさき | 1954 | 芥 | 123 | 2000上 | 花腐し |
| 松村栄子 | まつむら えいこ | 1961 | 芥 | 106 | 1991下 | 至高聖所(アバトーン) |
| 松本清張 | まつもと せいちょう | 1909 | 芥 | 28 | 1952下 | 或る「小倉日記」伝 |
| 丸谷才一 | まるや さいいち | 1925 | 芥 | 59 | 1968上 | 年の残り |
| 丸山健二 | まるやま けんじ | 1943 | 芥 | 56 | 1966下 | 夏の流れ |
| 三浦しをん | みうら しをん | 1976 | 直 | 135 | 2006上 | まほろ駅前多田便利軒 |
| 三浦清宏 | みうら きよひろ | 1930 | 芥 | 98 | 1987下 | 長男の出家 |
| 三浦哲郎 | みうら てつお | 1931 | 芥 | 44 | 1960下 | 忍ぶ川 |
| 三木卓 | みき たく | 1935 | 芥 | 69 | 1973上 | 鶸 |
| 水上勉 | みずかみ つとむ | 1919 | 直 | 45 | 1961上 | 雁の寺 |
| 三田誠広 | みた まさひろ | 1948 | 芥 | 77 | 1977上 | 僕って何 |
| 道尾秀介 | みちお しゅうすけ | 1975 | 直 | 144 | 2010下 | 月と蟹 |
| 光岡明 | みつおか あきら | 1932 | 直 | 86 | 1981下 | 機雷 |
| 皆川博子 | みながわ ひろこ | 1929 | 直 | 95 | 1986上 | 恋紅 |
| 宮尾登美子 | みやお とみこ | 1926 | 直 | 80 | 1978下 | 一絃の琴 |
| 宮城谷昌光 | みやぎたに まさみつ | 1945 | 直 | 105 | 1991上 | 夏姫春秋 |
| 宮原昭夫 | みやはら あきお | 1932 | 芥 | 67 | 1972上 | 誰かが触った |
| 宮部みゆき | みやべ みゆき | 1960 | 直 | 120 | 1998下 | 理由 |
| 宮本輝 | みやもと てる | 1947 | 芥 | 78 | 1977下 | 螢川 |
| 三好京三 | みよし きょうぞう | 1931 | 直 | 76 | 1976下 | 子育てごっこ |
| 三好徹 | みよし とおる | 1931 | 直 | 58 | 1967下 | 聖少女 |
| 向田邦子 | むこうだ くにこ | 1929 | 直 | 83 | 1980上 | 花の名前・かわうそ・犬小屋 |
| 村上元三 | むらかみ げんぞう | 1910 | 直 | 12 | 1940下 | 上総風土記・その他 |
| 村上龍 | むらかみ りゅう | 1952 | 芥 | 75 | 1976上 | 限りなく透明に近いブルー |
| 村田喜代子 | むらた きよこ | 1945 | 芥 | 97 | 1987上 | 鍋の中 |
| 村田沙耶香 | むらた さやか | 1979 | 芥 | 155 | 2016上 | コンビニ人間 |
| 村松友視 | むらまつ ともみ | 1940 | 直 | 87 | 1982上 | 時代屋の女房 |
| 村山由佳 | むらやま ゆか | 1964 | 直 | 129 | 2003上 | 星々の舟 |
| 室井光広 | むろい みつひろ | 1955 | 芥 | 111 | 1994上 | おどるでく |
| 目取真俊 | めどるま しゅん | 1960 | 芥 | 117 | 1997上 | 水滴 |
| 本谷有希子 | もとや ゆきこ | 1979 | 芥 | 154 | 2015下 | 異類婚姻譚 |
| モブ・ノリオ | もぶ のりお | 1970 | 芥 | 131 | 2004上 | 介護入門 |
| 森絵都 | もり えと | 1968 | 直 | 135 | 2006上 | 風に舞いあがるビニールシート |
| 森荘已池 | もり そういち | 1907 | 直 | 18 | 1943下 | 山畠・蛾と笹舟 |
| 森敦 | もり あつし | 1912 | 芥 | 70 | 1973下 | 月山 |
| 森禮子 | もり れいこ | 1928 | 芥 | 82 | 1979下 | モッキングバードのいる町 |
| 森田誠吾 | もりた せいご | 1925 | 直 | 94 | 1985下 | 魚河岸ものがたり |
| 八木義徳 | やぎ よしのり | 1911 | 芥 | 19 | 1944上 | 劉廣福 |
| 安岡章太郎 | やすおか しょうたろう | 1920 | 芥 | 29 | 1953上 | 悪い仲間・陰気な愉しみ |
| 山口瞳 | やまぐち ひとみ | 1926 | 直 | 48 | 1962下 | 江分利満氏の優雅な生活 |
| 山口洋子 | やまぐち ようこ | 1937 | 直 | 93 | 1985上 | 演歌の虫 |
| 山崎豊子 | やまざき とよこ | 1924 | 直 | 39 | 1958上 | 花のれん |
| 山下澄人 | やました すみと | 1966 | 芥 | 156 | 2016下 | しんせかい |
| 山田詠美 | やまだ えいみ | 1959 | 直 | 97 | 1987上 | ソウル・ミュージック・ラバーズ・オンリー |
| 山田克郎 | やまだ かつろう | 1910 | 直 | 22 | 1949下 | 海の廃園 |
| 山本一力 | やまもと いちりき | 1948 | 直 | 126 | 2001下 | あかね空 |
| 山本兼一 | やまもと けんいち | 1958 | 直 | 140 | 2008下 | 利休にたずねよ |
| 山本道子 | やまもと みちこ | 1936 | 芥 | 68 | 1972下 | ベティさんの庭 |
| 山本文緒 | やまもと ふみお | 1962 | 直 | 124 | 2000下 | プラナリア |
| 楊逸 | やん いー | 1964 | 芥 | 139 | 2008上 | 時が滲む朝 |
| 唯川恵 | ゆいかわ けい | 1955 | 直 | 126 | 2001下 | 肩ごしの恋人 |
| 柳美里 | ゆう みり | 1968 | 芥 | 116 | 1996下 | 家族シネマ |
| 結城昌治 | ゆうき しょうじ | 1927 | 直 | 63 | 1970上 | 軍旗はためく下に |
| 由起しげ子 | ゆき しげこ | 1900 | 芥 | 21 | 1949上 | 本の話 |
| 吉田修一 | よしだ しゅういち | 1968 | 芥 | 127 | 2002上 | パーク・ライフ |
| 吉田知子 | よしだ ともこ | 1934 | 芥 | 63 | 1970上 | 無明長夜 |
| 吉村萬壱 | よしむら まんいち | 1961 | 芥 | 129 | 2003上 | ハリガネムシ |
| 吉目木晴彦 | よしめき はるひこ | 1957 | 芥 | 109 | 1993上 | 寂寥郊野 |
| 吉行淳之介 | よしゆき じゅんのすけ | 1924 | 芥 | 31 | 1954上 | 驟雨・その他 |
| 吉行理恵 | よしゆき りえ | 1939 | 芥 | 85 | 1981上 | 小さな貴婦人 |
| 米澤穂信 | よねざわ ほのぶ | 1978 | 直 | 166 | 2021下 | 黒牢城 |
| 李恢成 | り かいせい | 1935 | 芥 | 66 | 1971下 | 砧をうつ女 |
| 李琴峰 | り ことみ | 1989 | 芥 | 165 | 2021上 | 彼岸花が咲く島 |
| 連城三紀彦 | れんじょう みきひこ | 1948 | 直 | 91 | 1984上 | 恋文 |
| 若竹千佐子 | わかたけ ちさこ | 1954 | 芥 | 158 | 2017下 | おらおらでひとりいぐも |
| 鷲尾雨工 | わしお うこう | 1892 | 直 | 2 | 1935下 | 吉野朝太平記 |
| 和田芳恵 | わだ よしえ | 1906 | 直 | 50 | 1963下 | 塵の中 |
| 渡辺淳一 | わたなべ じゅんいち | 1933 | 直 | 63 | 1970上 | 光と影 |
| 渡邊喜恵子 | わたなべ きえこ | 1913 | 直 | 41 | 1959上 | 馬淵川 |
| 綿矢りさ | わたや りさ | 1984 | 芥 | 130 | 2003下 | 蹴りたい背中 |
過去の直木賞・芥川賞 受賞作

検索可能!すべての芥川賞・直木賞作家の受賞作・受賞回・生まれ年・読み
芥川賞と直木賞の受賞作家一覧です。 1935年から現在までのすべての作家の名前の読み、生年、受賞回、受賞年、受賞作をまとめています。 それぞれの賞、受賞順のまとめは以下もご覧ください。 芥川賞・直木賞作家50音順一覧 初期状態は50音順です...
- 第170回受賞作品と候補作品詳細
- 第169回受賞作品と候補作品詳細
- 第168回受賞作品と候補作品詳細
- 第167回受賞作品と候補作品詳細
- 第166回受賞作品と候補作品詳細
- 第165回受賞作品と候補作品詳細
- 芥川賞全集でまとめ読み!(文藝春秋)第1~19巻まとめ
その他関連賞

新井賞とは?受賞作品のすべてと同日発表の直木賞・芥川賞受賞作品
新井賞とは 発表:1月/7月 主催:カリスマ書店員・新井見枝香 三省堂神保町本店(東京都千代田区)勤務の書店員・新井見枝香氏が店頭での販促を兼ねて、個人的に推したいと選定した本(主に小説など)を発表する為立ち上げ、2014年7月から始まった...
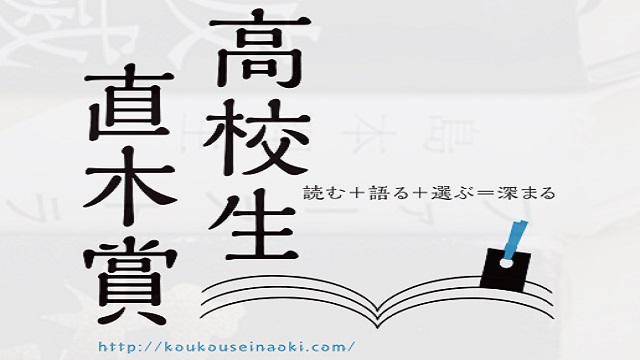
高校生直木賞とは?第1回(2014年)~現在までの受賞作品と候補作品のすべて
高校生直木賞とは 発表:4~5月 全国の高校生たちが集まって議論を戦わせ、直近1年間の直木賞の候補作から「今年の1作」を選ぶ試みです!! (公式サイトより引用) 高校生直木賞 主催:高校生直木賞実行委員会 後援:文部科学省、株式会社 文藝春...
売れ筋ランキング(Amazon)
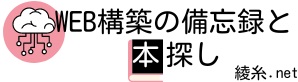


コメント